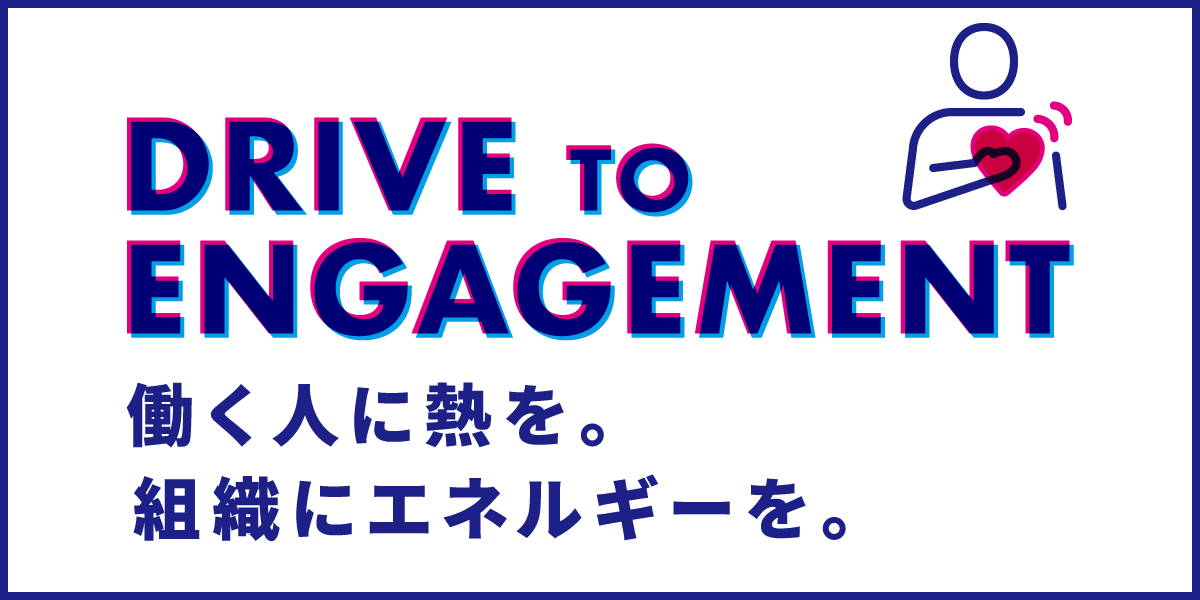新卒採用のコストはどのくらいかかる?費用対効果を高めるポイントとコスト削減の方法を解説
2025.07.09
企業の未来を担う人材を確保する新卒採用。それは、未来への重要な「投資」です。しかしその一方で、「思った以上にかかる採用コスト」に頭を悩ませている経営者様・人事担当者様も多いのではないでしょうか。
「新卒採用には、一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」
「コストの内訳を把握して、無駄をなくしたい」
「費用対効果の高い、賢い採用活動がしたい」
本記事では、新卒採用にかかるコストの全体像から、最新の平均費用、そしてコストを賢く削減するための具体的な方法まで、分かりやすく徹底解説します。
そもそも新卒採用のコストとは?「外部コスト」と「内部コスト」
新卒採用のコストを正確に把握するためには、まずコストが「外部コスト」と「内部コスト」の2種類に分類されることを理解する必要があります。
求人広告費やイベント出展費などの「外部コスト」
外部コストとは、社外のサービスや業者に対して支払う費用のことです。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・求人ナビサイトへの掲載料
・人材紹介サービスの成功報酬
・合同企業説明会への出展料
・採用パンフレットや動画の制作委託費
・採用管理システム(ATS)の利用料
これらは請求書などで金額が明確になるため、比較的管理しやすいコストと言えます。
採用担当者の人件費などの「内部コスト」
一方、内部コストとは、採用活動のために社内で発生する費用のことです。代表的なものは、採用担当者や面接官の人件費です。
・採用計画の策定、面接、内定者フォローなどにかかる人件費
・会社説明会の会場設営や運営にかかる人件費
・リファラル採用(社員紹介)のインセンティブ費用
・応募者との通信費や応募者の交通費
内部コストは、他の業務と兼務している担当者も多く、「見えにくい」コストとして見過ごされがちです。しかし、採用活動には多くの社員の時間と労力が費やされています。
なぜ両方のコストを把握することが重要なのか?
採用活動の費用対効果を正しく測定するためには、外部コストと内部コストの両方を合算して考えることが不可欠です。例えば、外部コストを削減するために求人広告費を削っても、その分を採用担当者がカバーすれば、内部コストである人件費が増大し、結果的に総コストは変わらない、あるいは増加してしまう可能性もあります。
両方のコストを可視化することで、初めて「どこにコストがかかり過ぎているのか」「どの施策が本当に効果的なのか」を判断できるようになるのです。
新卒採用のコストは平均いくら?
では、実際に企業は新卒採用にどれくらいのコストをかけているのでしょうか。
最新の調査データから見る採用単価の相場
株式会社マイナビが発表した「2024年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」によると、2024年卒の新卒採用における一人あたりの平均採用コスト(採用単価)は56.8万円でした。
(引用元:2024年卒マイナビ企業新卒内定状況調査)
これは、採用活動にかかった総費用(外部コスト+内部コスト)を、入社予定者数で割って算出された金額です。まずはこの数値を、自社のコストと比較する一つの目安としてください。
企業規模・業種によるコストの違い
同調査では、企業規模による違いも見られます。意外に思われるかもしれませんが、非上場企業の方が上場企業よりも採用単価が高くなる傾向にあります。これは、知名度で勝る大企業に比べて、中小企業は自社を認知してもらうための広報活動や、候補者一人ひとりに向き合うための工数に、より多くのコストがかかるためと考えられます。
また、業種によっても採用単価は変動します。特に専門的なスキルが求められる職種や、採用競争が激しい業界では、コストが高くなる傾向があります。
新卒採用コストの内訳を徹底解剖!主な費用項目一覧
ここでは、採用コストの具体的な内訳を「外部コスト」と「内部コスト」に分けて、さらに詳しく見ていきましょう。
【外部コスト】具体的な費用項目
- 求人広告費(ナビサイトなど)
数十万円から数百万円と、掲載するサイトの規模やプランによって大きく変動します。通年掲載プランや成功報酬型など、形態も様々です。 - 人材紹介サービス成功報酬
採用が決定した際に、紹介会社へ成功報酬を支払います。理論年収の30%~35%が相場とされています。 - 合同企業説明会・イベント出展費
大規模なものでは1ブース数十万円から数百万円かかることも。その他、ブース装飾費や配布物作成費も必要です。 - 採用ツール(ATS)利用料
ATS(Applicant Tracking System:採用管理システム)の利用料です。応募者情報の一元管理や選考進捗の自動化ができ、月額数万円から利用できるサービスが増えています。 - 採用パンフレット・動画などの制作費
企業の魅力を伝えるために不可欠なツールです。制作会社に依頼する場合、パンフレットは数十万円から、動画は簡易なもので10万円程度から制作可能です。
【内部コスト】見落としがちな費用項目
- 採用担当者・面接官の人件費
最も大きな割合を占める内部コストです。「(担当者の月給 ÷ 労働時間) × 採用活動に従事した時間」で算出します。面接官の工数も忘れずに計上しましょう。 - リファラル採用のインセンティブ費用
社員からの紹介で採用が決まった場合に、紹介者の社員へ支払う報奨金です。一人あたり5万円~10万円程度が相場です。 - 内定者フォローの費用(懇親会、研修など)
内定辞退を防ぐための重要な投資です。懇親会の飲食代や、内定者研修の運営費、交通費などが含まれます。 - 採用活動に伴う交通費・通信費
候補者の面接交通費の支給や、担当者の移動費、書類の郵送費など、細かな費用も積み重なると大きな金額になります。
新卒採用のコストを賢く削減する7つの方法
コストの内訳を把握できたら、次はいよいよコスト削減です。ここでは、単なる節約ではなく、採用の質を落とさずにコストを最適化するための7つの方法を、すぐに実践できるアクションプランと共に詳しくご紹介します。
1. 採用ターゲットを明確にし、ミスマッチを防ぐ
コスト削減の最も重要な第一歩は、ミスマッチによる早期離職(=採用コストの全損失)を防ぐことです。そのためには「誰を採用したいのか」という採用ターゲットを、解像度高く定義する必要があります。
- なぜ有効か?
ターゲットが明確になれば、求人広告のキャッチコピーや説明会の内容が、求める人材に「刺さる」ものになります。応募者の母集団の質が向上し、選考の効率が上がるだけでなく、入社後の定着率向上にも繋がり、再募集にかかるコストを削減できます。 - 具体的なアクションプラン
活躍する社員へのヒアリング
まずは自社で高いパフォーマンスを発揮している社員に、「入社の決め手は何か」「仕事のどんな点にやりがいを感じるか」などをヒアリングし、共通項を探しましょう。
ペルソナシートの作成
年齢や専攻といった基本情報だけでなく、価値観、性格、情報収集の方法といった内面まで具体化した架空の人物像(ペルソナ)を作成します。
「合わない人物像」も定義する
「求める人物像」と同時に「自社の風土には合わない人物像」も言語化しておくと、選考時の判断基準がよりシャープになります。
2. 採用歩留まりを分析し、ボトルネックを改善する
採用活動を「なんとなく」で進めていませんか?各選考フローの通過率(=歩留まり)を数値化することで、どこに問題があるのか(ボトルネック)が客観的に見えてきます。
- なぜ有効か?
例えば「面接後の辞退率が50%」という課題が分かれば、打つべき対策は「求人広告の追加出稿」ではなく「面接内容の改善」であると判断できます。非効率な部分に無駄なコストを投下するのを防ぎます。
- 具体的なアクションプラン
歩留まりの算出
Excelなどで「説明会参加者数」「書類選考応募者数」「一次面接参加者数」「最終面接参加者数」「内定者数」を記録し、各段階の通過率を計算します。(例:面接通過率 = 面接通過者数 ÷ 面接参加者数)
原因の仮説と対策
・書類通過率が低い場合
原因仮説:応募のハードルが高すぎる?
対策:募集要項の「必須条件」を絞り込み、「歓迎条件」と分ける。
・面接後の辞退率が高い場合
原因仮説:面接官の印象が悪い?魅力付けが不足している?
対策:面接官トレーニングを実施する。現場社員と気軽に話せる座談会を設ける。
3. オンライン採用(Web面接・説明会)を積極的に活用する
オンラインの活用は、もはやコスト削減のスタンダードです。特に中小企業にとってメリットは計り知れません。
- なぜ有効か?
説明会や面接をオンライン化するだけで、会場費、資料の印刷代、担当者や候補者の移動交通費といった物理的なコストを大幅に削減できます。また、居住地に関わらず優秀な学生にアプローチできるため、母集団形成の観点からも非常に有効です。 - 具体的なアクションプラン
ハイブリッド型から始める
全てをオンライン化するのに抵抗がある場合は、「一次面接はオンライン、最終面接はじっくり対面で」といったハイブリッド型から試してみましょう。
無料ツールを活用する
Google MeetやZoomといった無料でも十分に使えるツールからスモールスタートしてみるのがおすすめです。
丁寧なフォローを心がける
オンラインでは企業の雰囲気が伝わりにくい側面もあります。面接の前後に担当者から一言フォローのメールを入れるなど、対面以上の丁寧なコミュニケーションを意識しましょう。
4. リファラル採用(社員紹介制度)を導入・活性化する
社員の個人的な繋がりを活かすリファラル採用は、コストパフォーマンスが非常に高い手法です。
- なぜ有効か?
求人広告費や人材紹介会社への成功報酬が一切かからないため、採用単価を劇的に抑えることができます。また、社員が自社の魅力や実情を理解した上で紹介するため、カルチャーフィットしやすく、定着率も高い傾向にあります。 - 具体的なアクションプラン
魅力的な制度設計
紹介してくれた社員、入社した社員の双方にインセンティブ(報奨金や特別休暇など)を用意すると、協力が得やすくなります。
情報発信と協力依頼
全社会議や社内報などで制度の目的やメリットを丁寧に説明し、協力を呼びかけましょう。「こんな人に声をかけてほしい」という人物像を具体的に共有することが重要です。
紹介のハードルを下げる工夫
社員が友人に共有しやすいように、簡単な会社説明資料や紹介用のメッセージテンプレートを準備しておくと、活動が活性化します。
5. ダイレクトリクルーティングで「攻めの採用」へ転換する
求人広告を出して応募を「待つ」のではなく、企業側から候補者に直接アプローチする「攻め」の手法です。
- なぜ有効か?
自社が求める人材にピンポイントでアプローチできるため、不特定多数に向けた広告よりも費用対効果が高くなる可能性があります。企業の知名度に左右されず、候補者に直接熱意を伝えられる点も中小企業にとって大きなメリットです。 - 具体的なアクションプラン
スカウトメールの工夫
テンプレートの文章をそのまま送るのではなく、候補者のプロフィールをしっかりと読み込み、「あなたの○○という経験に魅力を感じました」と、パーソナライズされたメッセージを送ることが開封・返信率を高める鍵です。
効果測定と改善
送信したスカウトメールの開封率や返信率を分析し、「どんな件名だと開封されやすいか」「どんな内容だと返信が来やすいか」を常に改善していく運用が成功に繋がります。
6. 採用サイトやSNSなど自社オウンドメディアを強化する
自社の採用サイトやブログ、SNSは、広告費をかけずに企業の魅力を発信できる「資産」です。
- なぜ有効か?
オウンドメディア経由の応募が増えれば、高額な求人広告への依存度を下げることができます。また、仕事内容だけでなく、社風や社員の人柄といった「リアルな情報」を発信し続けることで、候補者の入社意欲を高め、入社後のギャップを防ぐ効果もあります。 - 具体的なアクションプラン
発信するコンテンツ例
・社員インタビュー(仕事のやりがい、失敗談、キャリアパスなど)
・「若手社員の一日」といったVlog風の動画コンテンツ
・社内イベントや福利厚生の紹介
・社長や役員が自らの言葉でビジョンを語るメッセージ
すぐに始められる工夫
高額な費用をかける必要はありません。まずはスマートフォンのカメラで撮影した写真や動画からでも、企業の「素顔」を伝えることは十分に可能です。
7. 採用代行(RPO)サービスを戦略的に利用する
採用活動の一部または全部を外部の専門家に委託するサービスです。
- なぜ有効か?
応募者対応や面接日程の調整といったノンコア業務をアウトソースすることで、採用担当者は面接や内定者フォロー、採用戦略の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できます。結果として、担当者の見えない人件費(内部コスト)を最適化し、採用活動全体の質を高めることができます。 - 具体的なアクションプラン
任せる業務を切り分ける
自社の課題が「人手不足」なのか「ノウハウ不足」なのかを明確にし、どこを任せるかを決めましょう。(例:スカウトメールの送信代行だけを依頼する、面接日程の調整だけを依頼する、など部分的な利用も可能です)
サービス選定
自社の課題に合わせて、料金体系や得意領域(IT業界に強い、など)を比較検討し、最適なパートナーを選びましょう。
費用対効果を高める新卒採用コストの考え方
ここまでコスト削減の方法をお伝えしてきましたが、最も大切なのは「費用対効果」という視点です。やみくもに費用を削ることが、必ずしも良い結果を生むとは限りません。
「かけるべきコスト」と「削減すべきコスト」を見極める
例えば、候補者が直接触れる企業のパンフレットやWebサイト、候補者の入社意欲を大きく左右する内定者フォローなどは、安易に削るべきではない「かけるべきコスト」と言えるでしょう。一方で、効果の薄い求人広告や、慣例で続けているだけのイベント出展などは、「削減すべきコスト」の候補です。自社の採用戦略において、何が重要かを見極めることが肝心です。
採用ブランディングへの投資が、中長期的なコスト削減につながる
「この会社で働きたい」と候補者から思ってもらえるような魅力的な会社であること、すなわち「採用ブランディング」への投資は、短期的にはコスト増に見えるかもしれません。しかし、企業のファンが増えれば、応募者の質と量が向上し、将来的には広告費などに頼らない採用が可能になります。これは、最も効果的なコスト削減策の一つなのです。
新卒採用のコストに関するご相談なら「jinji+」
本記事では、新卒採用にかかるコストについて、その内訳から平均費用、具体的な削減方法までを解説してきました。
新卒採用コストの管理は、単なる経費削減ではありません。自社の新卒採用活動を見つめ直し、より効果的な戦略を立てるための重要なプロセスです。
しかし、
「自社の採用コストが適正か分からない」
「コスト戦略について、何から手をつけたら良いかプロの意見が聞きたい」
このようにお考えの人事ご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「jinji+(ジンジプラス)」にご相談ください。
「jinji+」は、単なる採用支援にとどまりません。戦略の立案から、ターゲットに合わせた最適な手法のご提案、実行、効果測定、そして採用コストの最適化まで、採用活動全体を一気通貫でサポートいたします。
お客様一社一社の状況や課題を丁寧にヒアリングし、貴社の状況に合わせた最適なコストで、採用プランをご提案します。
新卒採用のコストに関するご相談にとどまらず、採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。