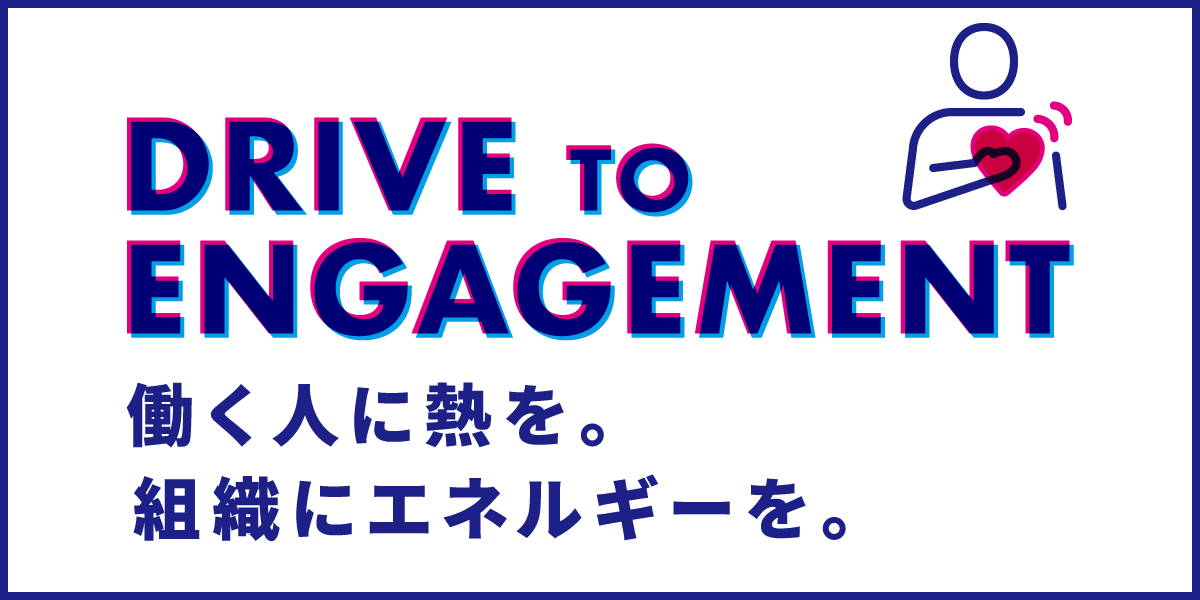新卒採用の手法14選!自社に合う選び方と成功のコツ
2025.07.09
近年、売り手市場が継続し、学生の価値観も多様化する中で、多くの経営者様、人事ご担当者様が「今まで通りのやり方では、なかなか学生が集まらない」「そもそも、どんな採用手法があるのか分からない」といった悩みをお持ちではないでしょうか。
この記事では、数ある新卒採用の手法を網羅的にご紹介するとともに、『自社にとっての正解』を見つけるための選び方のポイントを、採用のプロの視点から分かりやすく解説します。
なぜ今、新卒採用の手法の見直しが必要なのか?
まず、なぜ従来の手法だけでは通用しなくなりつつあるのでしょうか。その背景には、大きく2つの変化があります。
変化する学生の就職活動
現在の学生は、スマートフォンを駆使して情報を集めるデジタルネイティブ世代です。企業の公式サイトや就職ナビサイトだけでなく、SNSや口コミサイトで「リアルな情報」を収集するのが当たり前になっています。
また、企業選びの軸も変化しており、企業の安定性や規模だけでなく「企業のビジョンや社会貢献性への共感」「自身の成長環境」「働き方の柔軟性」といった点を重視する傾向が強まっています。企業の表面的な情報だけでは、学生の心を掴むことは難しくなっているのです。
採用市場の競争激化と「攻めの採用」の重要性
少子化の影響もあり、採用市場は学生優位の「売り手市場」が続いています。これは、学生からの応募をただ「待つ」だけでは、求める人材に出会うこと自体が困難になっていることを意味します。
そこで重要になるのが、企業側から学生にアプローチする「攻めの採用」への転換です。ダイレクトリクルーティングやSNS採用といった新しい手法が注目されているのは、まさにこの「攻めの採用」を実践するための有効な手段だからです。
新卒採用の主な手法14選
では、現在新卒採用で使われている手法にはどんなものがあるのか、従来の代表的な手法から近年注目される新しい手法、その他ユニークな手法まで幅広く紹介します。
従来型の代表的な手法
1. 就職ナビサイト(リクナビ・マイナビなど)
リクナビやマイナビを代表とする、多くの学生が登録・利用する採用ポータルサイトです。
メリット: 圧倒的な登録者数を誇るため、幅広い学生へのアプローチが可能で、大規模な母集団形成に繋がります。
デメリット: 掲載企業数が非常に多く、他社の情報に埋もれやすい点が挙げられます。また、掲載プランによってはコストが高額になる傾向があります。
2. 合同企業説明会
大規模な会場に多くの企業が集まり、ブース形式で学生に自社をPRするイベントです。
メリット: 一度に多くの学生と直接コミュニケーションを取ることができ、企業の認知度向上に繋がります。
デメリット: 参加学生の志望度は様々で、自社への興味が薄い層も多く含まれます。また、出展費用や当日の人件費といったコストがかかります。
3. 人材紹介(エージェント)
採用エージェントが、企業の求める条件に合った学生を個別に紹介してくれるサービスです。
メリット: 成功報酬型が多く、採用が決定するまで費用が発生しません。また、エージェントによるスクリーニングを経た、比較的質の高い学生に会うことができます。
デメリット: 採用決定時の紹介手数料が高額になるケースがあります。また、採用活動のノウハウが社内に蓄積されにくい側面があります。
4. 大学のキャリアセンター(学内推薦)
各大学に設置されているキャリアセンターや就職課と連携し、求人票の掲示や学内説明会の開催、推薦依頼などを行う手法です。
メリット: 無料で求人票を提出できる大学が多く、特定の大学の学生に的を絞ってアプローチできます。大学との強固なパイプを築くことで、安定した採用に繋がる可能性があります。
デメリット: 担当者との関係構築に時間がかかります。また、効果が特定の大学に限定されやすいです。
近年注目される新しい手法
5. ダイレクトリクルーティング
企業側が学生のデータベースにアクセスし、会いたい学生を探して直接スカウトメッセージを送る「攻め」の手法です。
メリット: 求める人物像に直接アプローチできるため、採用のミスマッチが起こりにくいです。就職ナビサイトに比べ、採用コストを抑えられる可能性があります。
デメリット: 学生のプロフィール確認やスカウト文面の作成・送信など、運用に工数がかかります。
6. SNS採用(ソーシャルリクルーティング)
X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどを活用して企業の情報を発信し、学生とコミュニケーションを取る手法です。
メリット: 企業のリアルな雰囲気や文化を伝えるのに適しており、学生の共感を醸成しやすいです。潜在的な候補者層にもアプローチが可能です。
デメリット: 継続的な情報発信の工数がかかり、いわゆる「炎上」のリスクも伴います。
7. リファラル採用(社員紹介)
自社の社員に、知人や友人を紹介してもらう手法です。
メリット: 社員のお墨付きがあるため、カルチャーフィットしやすく定着率が高い傾向にあります。採用コストを大幅に削減できる点も大きな魅力です。
デメリット: 人間関係のしがらみから、不採用時の対応に配慮が必要です。また、紹介を促進するための制度設計や社員への周知が不可欠です。
8. 採用イベント・ミートアップ
企業が独自に開催する小規模な説明会や座談会、オフィス見学会などです。
メリット: 学生と近い距離でじっくり話せるため、相互理解が深まります。企業の魅力を熱意をもって直接伝えられる場です。
デメリット: 企画から集客、運営まで自社で行う必要があり、工数がかかります。
9. インターンシップ
学生に実際の就業体験を提供し、仕事への理解を深めてもらうプログラムです。
メリット: 学生のスキルや人柄、仕事への適性を深く見極められます。入社後のミスマッチを防ぐ効果が非常に高い手法です。
デメリット: 学生を現場で受け入れる体制の構築や、魅力的なプログラムの企画・運営に工数がかかります。
10. 採用オウンドメディア・ブログ
自社で運営するブログやWebサイトで、社員インタビューや企業文化、働き方など、自社の魅力を自由に発信する手法です。
メリット: 発信したコンテンツは企業の「資産」として蓄積され、継続的な集客効果が期待できます。広告では伝えきれない深い情報を届けられます。
デメリット: 効果が出るまでに時間がかかります。また、質の高いコンテンツを継続的に制作する労力が必要です。
11. 動画コンテンツの活用
YouTubeや採用サイト上で、会社紹介や社員インタビュー、オフィスの様子などを動画で配信する手法です。
メリット: テキストや写真だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や社員の人柄が直感的に伝わります。情報量が多く、学生の記憶に残りやすいです。
デメリット: 動画の企画や撮影、編集には専門的な知識や機材が必要で、外注するとコストがかかります。
12. 逆求人サイト
学生が自身のプロフィールやスキル、経験を登録し、それを見た企業側が「いいね」や面接のオファーを送るサイトです。
メリット: 自己PRを積極的に行っている、意欲の高い学生に出会える可能性があります。学生からのアプローチを待つ形になるため、効率的です。
デメリット: サービスによっては、まだ登録学生の数が多くないことや、登録学生の希望職種が限定的な場合があります。
その他ユニークな手法
13. 地方学生向け採用
オンラインでの説明会や面接を積極的に活用したり、地方都市で小規模な採用イベントを実施したりするなど、Uターン・Iターン就職を希望する学生にアプローチする手法です。
14. オンライン面接・Web説明会
厳密には選考プロセスの一部ですが、オンライン化することで、居住地に関わらず多くの学生が選考に参加しやすくなります。結果として、母集団の拡大に繋がる重要な手法となっています。
自社に合った新卒採用手法の選び方
これだけ多くの手法があると、どの手法を選べば良いか迷ってしまいます。そこで、自社に最適な手法を見つけるためのステップをご紹介します。
採用目標とペルソナ(求める人物像)を明確にする
まず取り組むべきは、「誰を・何名」採用したいのかを具体的にすることです。
採用人数(量): 今年度は何名採用したいのか。
ペルソナ(質): どんなスキル、経験、価値観を持つ人材に来てほしいのか。
特にペルソナ設定では、スキルだけでなく「どんなことに喜びを感じ、どんな働き方を望んでいるか」まで解像度を高く持つことが、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。そのペルソナが、普段どんなツールで情報収集しているかを想像することが、手法選びの第一歩となります。
採用にかけられる「コスト」と「工数」を把握する
次に、自社のリソースを現実的に評価します。
コスト: 採用活動全体にかけられる予算はいくらか。
工数: 人事担当者は何名か。採用活動にどれくらいの時間を割けるか。
マンパワー不足は、多くの企業様が抱える共通の課題です。新しい手法に挑戦したくても、日々の業務に追われて手が回らないというケースも少なくありません。すべてを自社で抱え込まず、必要に応じて採用のプロ(アウトソーシング)を頼ることも賢い選択肢の一つです。
複数の手法を組み合わせる(採用ポートフォリオの考え方)
一つの手法にすべてを賭けるのは、リスクが高い選択です。それぞれのメリット・デメリットを補い合えるよう、複数の手法を組み合わせる「採用ポートフォリオ」の考え方を取り入れましょう。
採用活動をフェーズで分け、それぞれに合った手法を配置するのがポイントです。
認知拡大フェーズ(広く浅く): 就職ナビサイト、合同説明会、SNS
興味喚起・関係構築フェーズ(狭く深く): ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、採用イベント
例えば、「就職ナビサイトで広く認知を取りつつ、特に会いたい学生にはダイレクトリクルーティングで直接アプローチする」といった組み合わせが効果的です。
どの手法でも共通!新卒採用を成功に導くための重要ポイント
最後に、どの手法を選ぶにしても、成功のために共通して押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。
1. 学生の心をつかむ採用サイト・コンテンツの準備
各採用手法は、あくまで学生に自社を知ってもらうための「入口」です。興味を持った学生が必ず訪れる「受け皿」、つまり魅力的な採用サイトやコンテンツがなければ、せっかくの機会を逃してしまいます。学生が本当に知りたい事業内容、働きがい、社員の声、キャリアパスといった情報を充実させましょう。
2. 候補者体験(Candidate Experience)の向上を意識する
候補者体験とは、学生が企業を認知してから選考を経て入社に至るまでの、すべての接点における体験価値のことです。「選考結果の連絡が早い」「面接官が親身に話を聞いてくれた」といったポジティブな体験は、志望度を大きく高めます。反対に、ネガティブな体験はSNSで拡散されるリスクもあり、丁寧で誠実なコミュニケーションがこれまで以上に重要です。
3. データに基づいた効果測定と改善を繰り返す
採用活動を「やりっぱなし」にしないことも大切です。「どの手法からの応募者が内定承諾に至りやすいのか」「手法ごとの採用単価(費用対効果)はどうだったのか」を必ずデータで振り返りましょう。このPDCAサイクルを回すことで、次年度の採用戦略の精度が格段に向上します。
新卒採用の手法に関するご相談なら「jinji+」
新卒採用の手法は多様化していますが、最も重要なのは、自社の状況を正しく理解し、目標達成のために最適な手法を主体的に選択・実行していくことです。
しかし、
「自社に最適な採用手法がわからない」
「採用のマンパワーが足りず、新しい手法に挑戦できない」
このようにお考えの人事ご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「jinji+(ジンジプラス)」にご相談ください。
「jinji+」は、単なる採用支援にとどまりません。採用戦略の立案から、ターゲットに合わせた最適な新卒採用手法のご提案、実行、効果測定、そして改善まで、採用活動全体を一気通貫でサポートいたします。
お客様一社一社の状況や課題を丁寧にヒアリングし、豊富な実績とノウハウに基づいた最適なプランをご提案。適切な手法によって採用を成功させるべく、二人三脚で伴走し、寄り添った改善をいたします。
新卒採用の手法に関するご相談にとどまらず、採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。