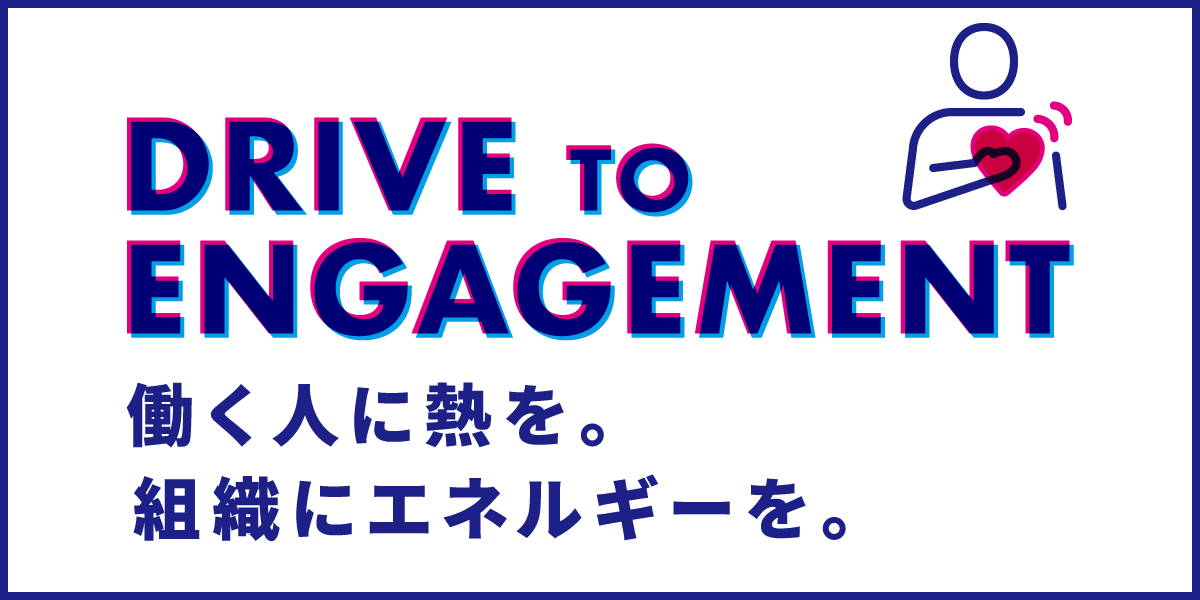新卒採用におけるスカウト活用とは?成功のコツを徹底解説
2025.07.23
ナビサイトに掲載するだけの「待ち」の採用では、求める人材に出会うことが難しくなっていませんか?売り手市場が続くいま、新卒採用を成功させる鍵は、企業から学生へ直接アプローチする「攻め」の採用、すなわち「スカウト採用」にあります。
しかし、「スカウトは手間がかかりそう」「どんな文章を送れば良いかわからない」といった不安から、一歩を踏み出せないでいる経営者・人事担当者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、新卒採用におけるスカウトの基礎知識から、返信率を高めるメールの書き方、成功のための具体的な運用方法まで、中小企業の経営者・人事担当者様に向けて分かりやすく解説します。
新卒採用における「スカウト」とは?
新卒採用におけるスカウトとは、企業側が自社の求める要件に合う学生を探し出し、直接アプローチする「攻めの採用手法」です。ダイレクトリクルーティングとも呼ばれ、近年多くの企業が導入を進めています。
従来のナビサイトとの違い
従来主流だった就職ナビサイトは、企業が情報を掲載し、学生からの応募を「待つ」のが基本です。これは、いわば「待ちの採用」です。 一方、スカウトは企業が人材データベースなどから候補者を探し、直接アプローチをかける「攻めの採用」です。この能動的なアプローチが、両者の最大の違いと言えるでしょう。
ダイレクトリクルーティングとの関係性
「スカウト」と「ダイレクトリクルーティング」は、しばしば同義で使われますが、厳密には少し異なります。
- ダイレクトリクルーティング: 企業が外部の人材紹介会社などを介さず、候補者と直接コミュニケーションをとる採用活動全般を指す、より広い概念です。
- スカウト: ダイレクトリクルーティングを実現するための、具体的なアプローチ手法の一つです。
この記事では、ダイレクトリクルーティングの中核をなす「スカウト」に焦点を当てて解説を進めます。
新卒採用でスカウトを活用すべき3つのメリット
それでは、なぜ今、スカウト採用がこれほどまでに注目されているのでしょうか。特に中小企業にとって、活用すべきメリットは大きいと言えます。
ナビサイトにはいない「潜在層」の優秀な学生に出会える
就職活動を本格化させていない学生や、大手志向で中小企業を検索対象に入れていない学生の中にも、優秀な人材は数多く存在します。スカウト採用は、こうした「潜在層」に対して、企業側からその存在を知らせ、興味を持ってもらうきっかけを作ることができます。知名度では大手に及ばない中小企業にとって、これは非常に大きなメリットです。
一人ひとりに魅力を伝え、入社後のミスマッチを軽減できる
スカウトメールでは、学生一人ひとりのプロフィールや経験に合わせて、自社のどの部分に魅力を感じたのかを具体的に伝えられます。「あなたの〇〇という経験は、弊社の△△という事業で必ず活かせます」といったアプローチは、学生の心に響き、深い企業理解へと繋がります。 この丁寧なコミュニケーションは、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを減らす効果も期待できます。
採用単価を抑え、コストパフォーマンスを高められる
大規模な合同説明会への出展やナビサイトへの広告掲載は、多額の費用がかかる割に、求める人材と出会える保証はありません。 一方、スカウト採用は、ターゲットを絞って効率的にアプローチできるため、結果として一人当たりの採用コストを抑えられる可能性があります。費用対効果を重視する中小企業にとって、合理的な採用手法と言えるでしょう。
【関連記事】新卒採用のコストはどのくらいかかる?費用対効果を高めるポイントとコスト削減の方法を解説
新卒採用向けスカウトサービスの選び方の3つのポイント
スカウトを始めるには、まず専用のサービスに登録するのが一般的です。数あるサービスの中から自社に合ったものを選ぶために、以下の3つのポイントを押さえましょう。
登録学生の属性(文理、志向性、大学群など)
サービスによって、登録している学生の層は異なります。理系学生に特化したサービス、特定のスキルを持つ学生が集まるサービス、ベンチャー志向の学生が多いサービスなど様々です。自社が求める人物像と、サービスの登録学生層がマッチしているかを必ず確認しましょう。
料金体系(成功報酬型・定額型)
料金体系は、主に「成功報酬型」と「定額型」の2つに大別されます。
- 成功報酬型: 初期費用や月額費用はかからず、採用が決定した時点で費用が発生。
メリット:リスクが低い。
デメリット:採用人数が多いと割高になる。
- 定額型: 月額または年額で費用が固定されており、期間内であれば何人採用しても料金は変わらない。
メリット:採用人数が多いほど一人当たりの単価が下がる。
デメリット:一人も採用できなくても費用がかかる。
年間の採用目標が1〜2名であれば「成功報酬型」、3名以上であれば「定額型」を検討すると良いでしょう。
機能とサポート体制(運用代行の有無など)
「スカウトを送る時間がない」「効果的な文面が作れない」といった悩みを持つ企業は少なくありません。そうした場合は、スカウトの配信代行や、効果改善のコンサルティングといったサポートが充実しているサービスを選ぶのがおすすめです。自社のリソースと相談しながら、必要なサポートが得られるかを見極めましょう。
新卒採用におけるスカウトメールの作成ステップ
スカウトの成否は、メールの内容で9割決まると言っても過言ではありません。ここでは、学生の心を開き、返信に繋げるための5つのステップを例文付きで解説します。
ターゲット学生を明確にする
まずは、どんな学生にアプローチしたいのかを具体的に定義します。「明るく元気な人」といった曖昧なものではなく、「〇〇という経験を通じて、△△という価値観を持っている人」というレベルまで解像度を高く持つことが、後のステップの精度を高めます。
開封されるかが決まる「件名」の作り方
毎日多くのメールを受け取る学生にとって、件名は開封するか否かを判断する重要な要素です。
- NG例: 株式会社〇〇です。スカウトのご連絡。
→誰にでも送っている印象を与え、開封されにくい。 - OK例: 【株式会社〇〇】〇〇様のインサイドセールス経験に惹かれ、ご連絡しました。
→「自分宛て」であることが一目でわかり、興味を引く。
「あなたに送った」が伝わる本文の作成
本文で最も重要なのは、「なぜ、他の誰でもなく、あなたに連絡したのか」を具体的に伝えることです。
【例文】
件名:【株式会社Take Action】〇〇様のWebサービス開発経験に惹かれ、ご連絡いたしました。
〇〇様
はじめまして。株式会社Take Actionで代表をしております、△△と申します。
〇〇様のプロフィールを拝見し、特に「ユーザーの課題を技術で解決したい」という想いのもと、長期インターンでReactを用いたサービス開発に尽力されたご経験に大変感銘を受け、ぜひ一度お話させていただきたいと思い、ご連絡いたしました。
当社の主力事業である採用支援サービス「jinji+」も、まさに〇〇様が学習されてきた技術を用いて開発されています。何より、〇〇様のその想いは、当社の「採用から会社を強くする」というミッションと深く通じるものがあると感じております。
〇〇様のようなお力をお持ちの方であれば、当社の開発チームで即戦力としてご活躍いただけると確信しております。
ポイント:
- 学生のプロフィール(実績、経験、自己PRなど)の何に惹かれたのかを具体的に書く。
- 惹かれた理由と、自社の事業や理念との共通点を示す。
- 「あなただから連絡した」という特別感を演出する。
次のアクションを明確に提示する
メールの最後には、学生に何をしてほしいのかを分かりやすく示しましょう。ただし、「まずは書類選考へ」といきなり選考に誘導するのはハードルが高いです。
【例文】
もし少しでも当社にご興味をお持ちいただけましたら、まずは一度、オンラインでカジュアルにお話してみませんか?
当社の開発チームのリーダーを交え、より具体的な事業内容や開発環境についてお伝えできればと思っております。もちろん、これは選考ではございませんので、まずは情報交換の場として、お気軽にご検討いただけますと幸いです。
以下のURLから、ご都合の良い日時を15分ほどお選びください。[日程調整ツールのURL]
効果測定と改善を繰り返す
スカウトは送りっぱなしでは意味がありません。「開封率」「返信率」を定期的にチェックし、「どんな件名だと開封されやすいか」「どの文章だと返信が来やすいか」を分析し、常に改善を繰り返すことが成功への近道です。
新卒採用のスカウトを成功に導く3つの秘訣
スカウトは「チーム戦」。経営層も巻き込み全社で取り組む
スカウトは人事だけの仕事ではありません。特に中小企業では、社長や役員が自らの言葉で会社のビジョンを語るスカウトメールは、学生にとって非常に魅力的です。現場の社員に協力を仰ぎ、仕事のやりがいを伝えてもらうのも効果的です。全社を巻き込んで、一体感のある採用活動を行いましょう。
すぐに結果を求めない。長期的な視点で学生との関係を築く
一度スカウトを送って返信がなくても、諦めるのは早計です。すぐに就職活動を考えていない学生もいます。興味を持ってくれた学生とは、その後も定期的に情報を提供するなどして、接点を持ち続ける「ナーチャリング」の視点が重要です。
リソースが足りない場合は、外部の専門家(代行サービス)を頼る
「理想は分かるが、そこまで手が回らない」というのが、多くの中小企業の本音でしょう。その場合は、無理に自社だけで抱え込まず、採用代行(RPO)などの専門サービスを活用するのも有効な選択肢です。プロの力を借りることで、より効率的かつ効果的なスカウト活動が実現できます。
新卒採用のスカウトに関するご相談なら「jinji+」
本記事では、新卒採用におけるスカウトの重要性から、具体的な実践方法までを解説しました。
スカウト採用は、単なる採用手法の一つではなく、企業の未来を担う人材と早期に出会い、関係を築くための強力な戦略です。特に、知名度や採用体力で大手企業に劣る中小企業にとって、自社の魅力を深く、的確に伝えることができるスカウトは、採用成功の大きな武器となります。
しかし、
「自社の新卒のスカウトが適正か分からない」
「新卒採用のスカウト活用について、何から手をつけたら良いかプロの意見が聞きたい」
このようにお考えの人事ご担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「jinji+(ジンジプラス)」にご相談ください。
「jinji+」は、単なる採用支援にとどまりません。戦略の立案から、ターゲットに合わせた最適な手法のご提案、実行、効果測定、そしてスカウト活用まで、採用活動全体を一気通貫でサポートいたします。
お客様一社一社の状況や課題を丁寧にヒアリングし、貴社の状況に合わせた採用プランをご提案します。
新卒採用のスカウトに関するご相談にとどまらず、採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。